自立した消費者の育成と消費者市民社会の実現
消費者教育の推進
消費者教育は、皆さんが、消費生活に関する知識や技能を習得し、それを適切な行動に結び付け、自立して安全で豊かな消費生活を営めるようにするために行われるものです。そして、消費者教育は、主体的に、消費者市民社会の形成に参画し、発展に寄与できる人を育むものでもあります。
消費者教育を総合的・一体的に推進することを目的として、2012年12月に消費者教育推進法が施行されました。
この法律に基づき、2013年6月に閣議決定された「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(基本方針)では、誰もが、どこに住んでいても、学校・家庭・地域・職域など様々な場で、幼児期から高齢期までの生涯を通じて消費者教育を受けることができるように、国や地方公共団体はその機会を提供することとなっています。なお、基本方針については、その後の消費生活を取り巻く環境の変化や消費者教育の推進に関する施策の実施の状況を踏まえ、2018年3月及び2023年3月に変更されています。
消費者教育推進法に基づき設置された「消費者教育推進会議」(第6期:2023年10月~)では、社会経済情勢に応じた課題等について議論を行っています。また、消費者教育の担い手を支援するため、「消費者教育ポータルサイト」において、消費者教育で活用できる教材や出前講座を実施している団体情報の紹介等の情報発信を行っています。
- [消費者教育]消費者教育ポータルサイト
- https://www.kportal.caa.go.jp/
エシカル消費の普及啓発
消費者市民社会の構築の一環として、消費者庁では、エシカル消費の普及啓発にも取り組んでいます。エシカル消費とは、地域の活性化や雇用などを含む、人や社会・環境に配慮した消費行動を指し、突き詰めれば、消費者それぞれが、各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援したりしながら消費活動を行うことであるといえます。そして、SDGsの目標12「つくる責任、つかう責任」に掲げられている、消費者が持続可能な社会の形成に寄与するという視点に係る具体的な行動例です。
消費者庁では、サステナブルファッション等のエシカル消費の普及啓発として、地方公共団体の取組の後押しとなるよう、先進的な取組の収集・紹介、啓発パンフレットの作成や特設サイトの充実、多様な主体との協働による気運の醸成などに取り組んでいます。
- [エシカル消費]サステナブルファッションに関する特設ページ
- https://www.ethical.caa.go.jp/sustainable/
グリーン志向の消費行動の促進
消費者庁では、これまでのエシカル消費の普及啓発の取組をさらに深化させていくために、地球環境分野に着目して、消費者が地球環境に配慮された商品・サービスを理解し、意識的に選択する「グリーン志向の消費行動」を促すための取組を進めています。
令和6年11月から、有識者で構成される「グリーン志向の消費行動に関するワーキングチーム」を開催し、課題の分析や今後の取組の方向性について議論・整理を行いました。
ワーキングチームでの議論・整理を踏まえて、まず手始めに、消費者・事業者・行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育などの各種事業が集中的に行う消費者月間(5月)などの機会を活用して、環境問題に関する危機感を共有し「自分事」と感じてもらうための発信や、身近なところから取り組むことができるグリーン志向消費の行動リストを使った啓発活動などに取り組んでいます。
- グリーン志向の消費行動に関するワーキングチーム
- https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/meeting_materials/review_meeting_009/
食品ロスの削減に向けた取組
エシカル消費の一環として、食品ロスの削減にも取り組んでいます。食品ロスとは、まだ食べることができるのに捨てられてしまう食品です。日本の食品ロス量は、年間472万トン(2022年度推計値)発生しており、このうち約半分は家庭から発生しています。
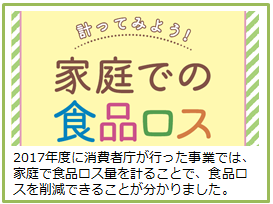
日本人一人当たりに換算すると、年間約38kg、毎日おにぎり1個分(約103g)の食べ物を捨てている計算になります。
家庭での食品ロスの主な理由として、
- 1食べきれなかった
- 2傷ませてしまった
- 3賞味・消費期限が切れていた
が挙げられます。
消費者庁では、日々の食事で必要な分だけ買う・作る、食べきれる工夫や飲食店での食べきり運動の促進、地方公共団体、民間企業や学生の皆さんによる様々な事例紹介などを通して、食べ物を無駄にしないよう食品ロス削減の取組を推進しています。
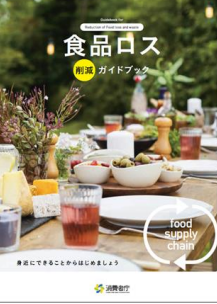
また、ライフスタイル、風習、産業など各地域特性に応じた食品ロス削減の推進に向け、地域で活躍していただける人材を育成する「食品ロス削減推進サポーター」制度を推進しています。本制度を推進していくため、消費者庁では、各サポーターの共通認識や活動の指針となるよう、食品ロス問題、食品ロス削減のコツ、事例紹介等を網羅的に掲載した教材「食品ロス削減ガイドブック」を作成しています。
このほか、外食時における食べ残しの持ち帰りの促進や食品寄附の信頼性向上に向けて、それぞれガイドラインを作成・公表しました。
また、「食品ロスの削減の推進に関する法律」に基づく「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」について、更なる削減の取組が進むように、具体的な施策を追加し、2025年3月に変更の閣議決定をしました。 具体的な施策には、2030年度までに、2000年度比で、事業者系食品ロスを6割減、家庭系食品ロスを半減する目標を設定しました。加えて、食品ロス削減に関する国際貢献の観点から、日本が国際社会をリードできるよう、国際的な組織との連携を通じた先駆的取組の共有により、国際展開を図ることなども盛り込んでいます。
消費者庁は、この基本的な方針に基づき、食品ロス削減に向けて、関係省庁、地方公共団体及び関係団体と連携しながら実施しています。
- [食品ロス削減]食べもののムダをなくそうプロジェクト
- https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/
- 食品ロス削減ガイドブック
- https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet#guidebook
- 食品ロスの削減の推進に関する法律等(「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」、「ガイドライン関係」)
- https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/












