消費生活の動向に関する調査と国際連携
消費生活の動向に関する調査
消費者白書
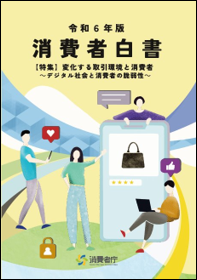
的確な消費者政策を企画立案するには、消費者を取り巻く環境と、意識や行動の変化について、調査・分析を行うことが不可欠です。
消費者庁は、毎年1回、こうした調査・分析の成果と、消費者政策の進捗の報告を取りまとめて、消費者白書として公表しています。
令和6年版の消費者白書では、「変化する取引環境と消費者~デジタル社会と消費者の脆弱性~ 」を特集テーマに、
- 消費者の脆弱性
- デジタル社会における課題と変化
などを取り上げました。
<過去の特集のテーマ>
- 令和6年版 変化する取引環境と消費者~デジタル社会と消費者の脆弱性~
- 令和5年版 高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組
- 令和4年版 変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取組 ~18歳から大人の新しい時代へ~
消費者意識基本調査
消費者問題の現状や求められる政策ニーズを把握し、消費者政策の企画立案にいかすことを目的として、年1回「消費者意識基本調査」を実施しています。若年層から高齢層までの合計1万人を対象に、日頃の消費生活での意識や行動、消費者事故・トラブルの経験等を調査しています。
消費生活意識調査
その時々のテーマについて消費者の意識や消費者トラブルの状況等を把握するため、「消費生活意識調査」を随時実施しています。若年層から高齢層までの合計5,000人を対象に、消費者の意識や行動、消費者政策の認知度等を調査しています。
国際的な取組
国際連携の推進
消費者問題は、デジタル時代において、世界共通の課題であることも少なくありません。
例えば、
- オンラインによる越境取引が増加する中、消費者トラブルが発生した場合に、一国だけでは解決が難しいという問題が発生しています。
- オンライン事業者によるウェブサイトやアプリ設計等により、消費者を誘導し、欺き、強要し又は操って、多くの場合、消費者の最善の利益とはならない選択を消費者に行わせる「ダーク・パターン」と呼ばれる手法は、海外でも国内でも問題になっています。
- 外国製品に安全上の問題があることが明らかになった場合、日本の消費者も早急に知る必要があります。
次々と現れる新しい消費者問題を迅速に把握して的確に対処するとともに、国境を越える消費者問題を防止・解決するには、外国当局との協力や連携が不可欠です。
このため、消費者庁は、OECD消費者政策委員会(OECD CCP)への参加や消費者保護及び執行のための国際ネットワーク(ICPEN)などの国際会議への参加を通じ、外国当局との意見交換を行っています。
【OECD CCP】
消費者政策に関する情報共有や加盟国間の協力の推進などを目的に1969年に設置され、約40か国が参加しています。2024年10月には、OECD初の消費者政策閣僚会合が「デジタル及びグリーン移行の中心にいる消費者」をテーマとして開催され、55の国・地域から消費者政策を担当する閣僚又は上級幹部が参加しました。日本からは内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)の代理として消費者庁長官が出席し、共通の課題について活発な意見交換を行いました。
国際共同研究として、2022年10月に「ダーク・パターン」 、2023年6月に「デジタル時代の消費者ぜい弱性」の報告書を公表しました。2024年には「ダーク・パターン」と共に「グリーン・トランジション」についても実証実験が行われ、近く報告書が公表される見通しです。
【ICPEN】
国境を越えた不正な取引行為を防止するため1992年に発足したネットワークで、約70か国の消費者保護関係機関が参加しています。
例えば、「econsumer.gov」プロジェクトでは、9か国語に翻訳したウェブサイトを通じて、世界中の消費者から寄せられた国境を越える詐欺に関する情報を収集・分析して、消費者への啓発を行っているほか、各国の対策にも活用されています。
- The OECD Committee on Consumer Policy (CCP)
- https://www.oecd.org/sti/consumer/
- ICPEN
- https://icpen.org/
- ICPEN econsumer.gov
- https://www.econsumer.gov/?lang=ja












