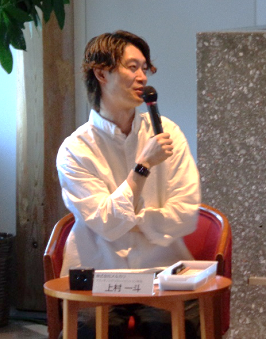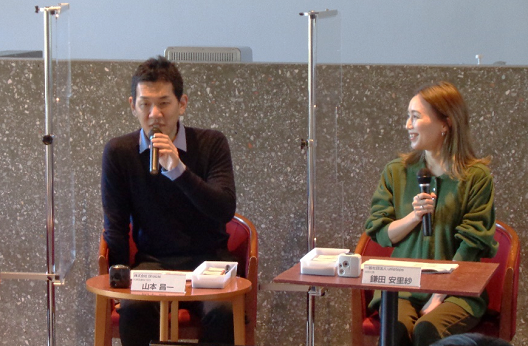【第2部】 「ファッションから考えるサステナブルな未来~わたしたちができること~」フォトレポート(トークショー・上勝町ゼロ・ウェイストセンターの取組紹介)
トークショー「わたしたちができるサステナブルファッション」
(コーディネーター:一般社団法人unisteps共同代表 鎌田 安里紗氏)
上勝町は全国平均で見ても非常に高いリサイクル率を誇る町。昨年2020年にこのゼロ・ウェイストセンターができた。ホテルとか、カンファレンスができる場所もあるが、町民の方が実際にごみを捨てに来る場所だ。今までごみを捨てる場所というのは、町の見えない場所とか外れに追いやられていたと思うが、ここではごみを捨てる場所に人が集まって、新しいことを考える場所になっている。
私は高校生の頃にアパレルの販売員のアルバイトを始めた。その時に自分が売っている服がどうやってできているか全然知らないなと思った。自ら調べたり、工場に足を運ぶようになって、洋服を作る場所がおもしろくなった。課題とおもしろさを両方伝えたいなと思い、いろいろと情報発信を続けてきた。
(ゲスト:株式会社メルカリ ブランディングコミュニケーション担当 上村 一斗氏)
世界中の個人と個人がつながって、資源を流通させることができればもっと豊かな暮らしができるのではないか。そう思って創業したのがメルカリ。世界中で誰かの不要品が必要としている誰かのもとに届くという世界を作るべく取り組んでいる。昨年の調査では、「購入したものの、その後ほとんど使わなくなったモノ」はだいたい半分くらいの方が「ある」と回答している。そのカテゴリとしては半分くらいが洋服。長く使ってもらうために、時にはメルカリを使うこともサステナブルなアクションの一つであることをぜひお伝えしたい。
(ゲスト:株式会社Shoichi 代表取締役CEO 山本 昌一氏)
Shoichiは法人の在庫処分ということを集中してやっている会社。ミッションとしては廃棄ゼロを実現してサステナブルな世界の実現に貢献するということ。メーカーやブランドがなぜ廃棄するかというと、安全な処分方法がない。いろんな問題があって方法がないから廃棄しているが、最近SDGsの流れで変わってきており、企業として捨てることの方がリスクになってきている。
(ゲスト:デプトカンパニー代表/アクティビスト eri氏)
デプトカンパニーという会社で、洋服を基本的には受注生産で、在庫を持たないという生産方法を採っている。素材といったものもなるべく地球環境に負担を掛けない作り方など、みなさんとシェアしながら生産をしている。
私が洋服を作るにあたって大事にしていることがある。1つ目は、物理的な耐久性。持続可能で着用できる洋服を作るというのがベースにある。2つ目が情緒的耐久性。そのものに対してどれだけ情緒的な感情を持てるかどうかで、そのものの寿命が決まると思っている。気持ちが強ければ強いほど、そのものが長生きすると思っている。
(鎌田氏)
今までは、希少なものを高いお金を出して買えるということが贅沢で喜びだったかもしれない。もしその価値を守るために余ったものを捨てているのだとしたら、それはもうまったく格好いいことじゃないという価値観の時代になった。物を買う人が愛着を抱けるきっかけを提供できる、物と自分が親密な関係を築けるきっかけを提供してくれているというのはこれからの贅沢の新しい形なのかもしれない。
(ゲスト:上勝町ゼロ・ウェイストセンター CEO 大塚 桃奈氏)
上勝町は2030年までに、「未来の子どもたちの暮らす環境を自分のことと考え、行動できる人づくり」を重点目標にしている。いままさにタウン計画が形成されていて、来年度以降から実行に移っていくというフェーズに入っている。上勝町の服を取り巻く現状を振り返ってみると、なるべく焼却・埋立ごみを無くすことを念頭に回収を行っている。まだ着ることができる衣服はセンター内にある「くるくるショップ(リユースショップ)」に持ち込まれ、手放したい衣服の状態が良いものは「衣類」として回収された後「ウエス」となり、汚れやほつれ等状態が悪いものは「その他の衣類」として「固形燃料」に生まれ変わっている。それぞれ「リサイクル」として回収されているが、ワンウェイのリサイクルになってしまっていたり、もともとその服が持っていた価値が下がっているダウンサイクルになっているとも言える。もっと価値のある循環にするためには、消費者ないし自治体がコストを負担しないと、その循環の選択肢が得られないというのが現状。
サステナブルファッションとして、1点目は、ものを作る段階では再資源化や再生が可能な素材をメーカーが利用することと、その回収先が整備された素材の利用を社会の中で促進するというような制度設計をしていくということ。2点目は、生活者が服を選ぶ基準となるような、共通の指針が販売時に提示されること。3点目は、ものを使う段階で、個人レベルで循環が体験できるようになるということ。作る段階に個人が関与できたり、それを分解する段階で関与できるような場をつくることで、もっと循環を身近に感じられるようになるのではと思う。
(鎌田氏)
一つ重要なポイントとして、手放すときの良い仕組みがないということ。もっと個人間の引渡しが進んだり、ものが廃棄されるまでの時間を伸ばしたり、あるいは廃棄することになっても良い循環を作れたり、こういったことが必要ではないか。
(上村氏)
物ができあがるまでのプロセスに関わることで愛着がわくことはすごいと思った。我々でいえば商品説明の欄に手間をかけずに思いやストーリーを載せられるというのはもっと仕組みとして何かがあればとヒントがあったと思う。
(山本氏)
例えば、セーターが原価3,000円として、100枚作ったら3,000円、だけと500枚作ったら2,500円、1,000枚作ったら2,200円ですと言われたら、多く作る方がお客さんに安く提供できることになる。その生産方式が変わらない限り、ファッション産業の課題が減るのは難しいと思う。ただ、売れ残ったら環境に悪いと思いながらも、良い商品を安く提供することは、やはり良いことだと思う。
(eri氏)
私は大量に作ることは反対しているが、この問題の解決は0、100ではなくグラデーションの中で起こっている。我々受け取る側がなぜ安いのか、それによる代償は何なのかを買う側が納得して、その背景にあることに自分たちが加担しているということをきちんと把握しているかという全体的なコンセンサスが取れていくべき。
(鎌田氏)
問題を知ると言うことは重要だが、頭で理解しているだけではなかなか行動に結びつきにくい。もう一歩踏み込んで、体感できる機会がないとなかなかアクションまでいかないのではないか。
(大塚氏)
ゼロ・ウェイストセンターには小さな宿があるが、ゼロ・ウェイストアクションをコンセプトにしている。最近はチェックインの時に施設の案内を必ず入れている。これによってこの町のストーリーや、ゼロ・ウェイストの取組をより理解して滞在していただく。上勝の特長として、ゴミステーションに行けばそれがどこに行って何になるのか、いくらでリサイクルされているのか、自分の行ったアクションが直結するというのが分かりやすく体験できる。
(鎌田氏)
登壇者それぞれの立場から見えている景色を共有し、個人ができることもあるし、システムとして変えて行かなければいけないこともあるということが改めて明確になった。こういうディスカッションの場を持つことも一つ重要なアクションだなと思った。私たちができるサステナブルファッションということで、聴いていただいた方も何か考えて、アクションするきっかけになれたら嬉しい。
上勝町ゼロ・ウェイストセンターの取組紹介

上勝町ゼロ・ウェイストセンター CEO 大塚 桃奈氏
もともとこの場所は町のゴミの中間処理施設だった。町でゼロ・ウェイスト宣言をしてからまだ焼却・埋立の課題があるという現状に加えて、町として過疎が進む中で人口の半分が高齢者という課題がある。その中で、どうしたらゼロ・ウェイストをきっかけに町の外からやってくる人と交流しながら、学び合って、ゼロ・ウェイストの選択肢を広げられるかということを検討して新しく公共複合施設が2020年5月にオープンしている。
町の方がここに自分の車でゴミを持ってきて、自分たちの手で分別しているという取組がある中で車の動線を考えた時にこの馬蹄状が生まれた。町の人だけでなく町外の方も滞在できるスペースを加えて鍵穴の形になり、「なぜ上勝からこの取組を発信していくのか」「なぜゴミはでるのか」といった問いを一緒に考える場所として「WHY」というキーワードが生まれて、建物が?の形になっている。
ゴミステーションにゴミが回収されて資源に分類されている。車で持って来れない方もいるので、2ヶ月に1回は収集の日が設けられている。みんなここにやってくるので、ゴミだけでなく、人も集まってくるコミュニティにとっても重要な場所になっている。
各家庭で生ゴミは堆肥として処理しているのと、汚れているプラスチックもみんなが洗って乾かして持ってくるという努力を重ねているので、いやな臭いはまったくしない。ゴミステーションの隣にはくるくるショップがあって、ここに町の方が手放したいがまだ使えるものを持ってきて、使いたい人が自由に持って帰れることができるという取組だ。これは町の小学生のアイデアで生まれた取組だ。信頼関係の中で物が行き交っている。
ショップにはルールが一つあって、持ち帰る時に必ず重さを量ってもらっている。そうすることによって年間を通じてどのくらいのものが新しい持ち主に受け渡っていったのかということを可視化している。今は町の方が持ち込むだけなのだが、今後は町外からも一緒に連携をして循環の選択肢が増やして行けたら良いなと思っている。
センターの壁面は窓がずらりと並んでいる。これは上勝町民から集めた窓になっている。いま町の人口がどんどん減っていって、町の灯りも消えかかっているともいえるけれども、ひとつひとつの灯りをまたここで集めて、ここから光を照らし出していけたらいいんじゃないかというメッセージが込められている。
交流ホールとホテルの間にあるラボラトリーは、オフィス空間として併設されている。上勝をベースに地域課題の解決や資源循環の実験などに取り組む企業を誘致し、活動を進めていく拠点として機能している。2022年の春からは、企業向けのオンラインセッションを行うなどメンバーシッププログラムも展開していく予定だ。
ゼロ・ウェイストアクションホテルHOTEL WHYは全部で客室が4つの小さな宿だ。ここの特徴としては使い捨てのアメニティを置いていないので、チェックインの時に計り分けのアクションに参加していただいたりとか、滞在しているときに出たゴミをチェックアウトの時にスタッフと一緒にゴミステーションで分別してもらうというような、分別をアトラクションにして一緒に楽しんでもらっている。
日々何気なく過ごしている時間とか使っている物とかを改めて振り返ってもらって、都市とは違う上勝の山の時間の中で、なぜ物は作られるのか、使われるのか、そして捨てられるのか、そんな何気ない疑問を持ちながら、自分たちにとっての心地よさ、世界にとっての心地よさをここから育んでいけたらいいなと思っているので、機会があればぜひゼロ・ウェイストセンターにお越しいただきたい。
担当:新未来創造戦略本部