【第1部】 「ファッションから考えるサステナブルな未来~わたしたちができること~」フォトレポート(開会挨拶・各省庁の取組紹介)
開会挨拶
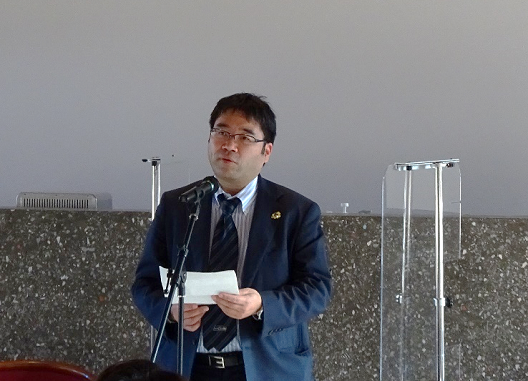
日下部消費者庁審議官(新未来創造戦略本部次長)
ファッション産業において衣服が年間約51万トン廃棄され、その97%が家庭から出たもの。ファッションを巡る課題解決には、衣料の原材料調達から、生産、流通、着用、廃棄に至るまで、環境負荷等に考慮した企業による取組はもちろん、実際に衣服を消費する消費者の意識行動も大変重要である。
消費者庁では、エシカル消費の普及、啓発の取組を進めており、その一環としてサステナブルファッションの取組も推進している。本日のイベントを通じてサステナブルファッションについて、私たち一人ひとりに何ができるかを考えていきたい。
各省庁の取組紹介

片岡消費者庁審議官
なぜ今サステナブルファッションか?
1点目は、SDGsの取組の中で、ファッションは環境負荷が非常に高いという点で世界で注目が高まっている。2点目は、消費者、特に若い人の間で地域のために何かしなければいけないという意識が高まってきている。3点目は、GDPが伸び悩む中で強靱な経済を作っていくために、質の高い商品を作っていかなければならない。4点目は、日本は世界の後塵を拝しているが「三方よし」「もったいない」という文化、優れた技術を持った日本だからこそ、世界をリードするべきであるということでこの運動を進めていかなければならない。
消費者庁の取組として、本日特にお伝えしたい取組は、1点目はサステナブルファッション特設ページを開設した。その中に、消費者行動18のヒントとして買う時、使っている時、処分する時のヒントを書いている。18のヒントに関連する事業者の取組について、順次掲載していく。2点目は「わたしのサステナブルファッション宣言」リレーである。こんなことをやっているとか、こんな事業者の取組を知っているということをハッシュタグを付けて投稿していただいている。
サステナブルファッションを実践するということではなくて、習慣化してライフスタイルにするということを世界へ示していきたい。また、各地域それぞれの様々なサステナブルファッションの取組があると思うが、時には競いながら高め合って、世界に発信していくということになれば良いと考える。
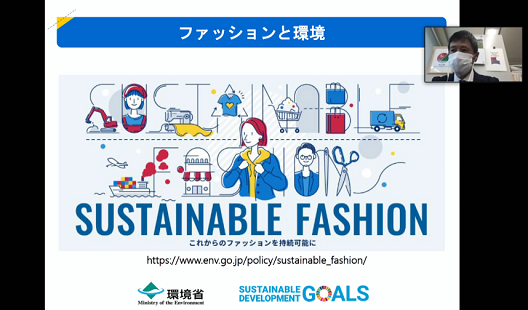
環境省「ファッションと環境」タスクフォースリーダー 岡野 隆宏氏
ファッション業界は世界で第二位の汚染産業とみなされている。さらにそういった多くの環境負荷を発生しながら作られた繊維製品が使われた後、多くがリユース、リサイクルされずに埋立や焼却になっている。それから環境負荷だけでなく、人権の問題もいろいろ指摘を受けている。
サステナブルファッションについての関心をアンケート調査すると、59.2%が「関心がある」と答えている。実際に具体的に取組を行ったのが4%で、9割は行動に移せてない。行動のために求められているのが、情報発信や回収・リペアなどの仕組み作りで、そういったところを整備することが課題となっている。
企業は企画の段階から環境配慮設計をする、生産の段階で透明性の確保、適量生産・適量供給に努める。生活者はそれに対して環境配慮製品を選択していく、所有しないで長く使用するサービスや古着などを長く着る。リサイクル技術の高度化という形で、循環していくことが目指すところかと考える。
SDGsの目指すところは、社会の変革である。そういった中でファッション産業は環境・社会・経済で課題を抱えている。一方でファッションは暮らしを彩り豊かにしてくれるもの、問題は「大量生産・大量消費・大量廃棄」であると考えている。
ファッションはまさに価値を創造し、時代を作るもの。時代の転換期にファッションの果たす役割は非常に大きいと思っている。目指すのは「適量生産・適量購入・循環利用」、そして「適正価格」。これを実現するには生活者と企業のコミュニケーション・協働がカギになっていく。
環境省としてはそのコミュニケーションにつながるよう、環境負荷の見える化のサポートなどに取り組んでいる。
また、循環利用など回収の仕組み作りといったものに取り組んでいきながら、生活者のライフスタイルシフトを後押ししていきたいと考えている。

経済産業省大臣官房審議官(製造産業局担当) 柴田 敬司氏
日本の繊維産業の市場規模は2/3程度に減少しており、事業数も5万超だったものが1万程度にまで減少している。その一方で繊維産業、特に素材部門を中心として、依然として世界と比べても強みを持っている分野はいろいろある。これをいかに活かしていくかは繊維産業にとっての課題だ。
経済産業省としても、サステナビリティについて従来から問題意識をもっている。1点目が環境配慮。循環経済への移行が重要であり、今後は経済産業省の大きな取組として、ガイドラインの策定といったものが重要だ。今のところ繊維分野における取組、その前提となる指標といったものについても統一的なものは無いというのが現状。どういったものが指標としてありうるのかといったことも含め、検討して、ガイドラインを業界と共に策定してくことが重要だ。
経済産業省は産業全体にかかるものとして循環システム、循環経済のビジョンを策定している。その中でも繊維産業は重要な分野として掲げられている。そこで2点目の問題は、供給構造をどうやって改善していくかといった点だと考える。今後の取組では、デジタル技術の活用が非常に重要なキーファクターになってくるのではと考えている。問題点の一つである在庫をいかに適切に管理していくかというところで、デジタル技術の果たしうる役割が非常に大きいと考える。
顧客を中心に置いた事業展開の推進、生産工程の改革、繊維産業の非常に長いサプライチェーンを効率化していく、こういったことをチャンスにしていく手段としてデジタル技術の活用もあると考えている。今後の日本経済、世界経済は、コロナにおけるサプライチェーンの断絶問題をどう解消していくか、カーボンニュートラルの問題、経済安全保障など、あらたな課題に直面している。その中に、本日のテーマである繊維分野でのサーキュラエコノミーというのが大きな課題だと思っている。経済産業省としても取組を今後とも進めていきたい考えだ。
担当:新未来創造戦略本部


